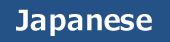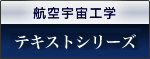第57期会長就任にあたって
このたび第57期の会長を図らずも拝命いたしました。輝かしいご活躍をしてこられた歴代会長と比較されると肩身が狭く、リーダーシップ溢れる中須賀真一前会長から重たいバトンを渡された思いですが、就任にあたり、会員の皆様にご挨拶を申し上げさせていただきます。
私は、これまで、統合前の宇宙科学研究所(ISAS)や統合後の宇宙航空研究開発機構(JAXA)で、衛星・探査機や輸送系の研究開発の現場を渡り歩いてきました。私のそもそもの専門分野は制御工学で博士論文は飛翔中のロケットのシステム同定に関するものでした。その博士論文研究がたいしたものではなかったこともあるのでしょう。ISASの助手となってからは衛星推進系開発への参加を求められたことを皮切りに、特定の分野に固執せずに活動してきました。宇宙関係限定ではありますが、多くの現場を経験し、様々な立場、多様な専門性の方々との交流をしてまいりました。そこで得た知見が少しでも学会の発展に貢献すれば、望外の喜びです。
言うまでもなく、日本航空宇宙学会は国内の航空分野、宇宙分野の学術に基づく諸活動を支える団体です。アカデミアや産業界の現場で活躍する正会員や大学等で研究活動をスタートした学生会員、更には日本や世界の将来を背負うジュニア会員などが、航空宇宙というキーワードで集う組織です。特に最近は、学術的知見をベースとしながらもそれだけに囚われずに、広く航空宇宙分野の発展を目指してきており、それが、学術シンポジウムの主催などと並行しての、航空宇宙技術遺産の認定や宇宙共創ビジネスアワードなどの活動に結びついています。今期も、この大きな流れをしっかりと継承しつつ、学会はどのようにあるべきか、学会の存在意義は何か、といった問いに対して、引き続き答えを探していく所存です。
広く言われていることですが、学術成果に関する情報が必要であれば、わざわざシンポジウムに足を運ぶまでもなく、ネット検索でかなりのものが得られる時代になって久しいのが現実です。もちろん、ネット検索では情報の正確性や質に疑問が生じることもあり、その点では、学会として情報をスクリーニングした上で発信し続けることの重要性は今後も変わらずあるでしょう。しかしながら、それだけでは時代の流れに取り残されかねません。やはり、それに加えて、まだ成果になっていないアイデアなどを生み出す場をつくる、そのため、多様なバックグランドの人間がフランクに集う機会を提供する、そういう機能が求められているのだろうと思います。自らの経験でも、ブレークスルーを得るようなアイデアは、自分とは異なる専門性、異なる立場、異なる考え方、更に性別など、多様な人間との交流の中で生み出されると実感しています。私事が続いて恐縮ですが、少し前に月面に着陸したSLIM(月面着陸実証機)を提案するにあたっては、学会のシンポジウムなどに出没し、一緒にやってくれそうな仲間を探したりしたものでした。将来のことまではわかりませんが、少なくとも現在は、予想もしない新たな出会いやその出会いを起爆剤としたアイデアの創出はネットで完結するものではなく、シンポジウムのように、優秀な人材が多く集まる場でのディスカッションが原動力なのだろうと思います。
このように考えると、学会は多様な人材が集い共創する機会を提供することが重要な使命に思えてきます。そのためにはどうすべきか。まず考えるべきは、学会の運営は、熱意ある多くの会員のボランティア活動の上に成り立っているという事実です。そういった献身的に学会を支えている諸会員がメリットを感じられると同時に、学会活動に何等かのワクワクを感じて積極的に参加頂くように微力ながら力を尽くしたいと思います。また、そういったボランティア活動で貢献する会員も、なるべく多様性をもった状態にしていくことが重要なのだろうと思います。みんなで無理なく、楽しく学会を支えている状態が理想なのだろうと思います。多くの会員が多様性をもって集まって学会を運営している姿は、学会そのものの姿にも現れてくると信じています。
理想の姿は一朝一夕に達成できるものでもないかもしれません。それでも、無理なく一歩ずつでも確実に前進していきたいと考えております。会員の皆様が自由闊達に活躍できる場を実現することを通して、本学会が日本の航空宇宙分野に留まらず、広く世の中に貢献できるよう微力ながら尽くしたいと思います。